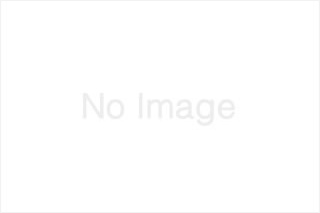11月4日、「パリ協定」はついに発効し、7日からは、細則などを決めるための国際会議COP22がモロッコのマラケシュで開始した。日本が国会で「パリ協定」の批准にもたついている間に、世界は大きく動き出したのだ。
振り返ってみると、90年代には日本は間違いなく世界の温暖化対策のトップグループにいた。90年10月には、法律もないのに、地球温暖化防止行動計画を日本政府は策定し、国民や企業に温暖化対策に参加することを呼び掛けていた。97年にはCOP3を日本の古都京都に招致し、温暖化対策の歴史的な第一歩である「京都議定書」を締結するホスト国としての力を世界に示した。まさにこのとき、トヨタはハイブリッド車プリウスを世界に向けて売り出している。
このように、90年代の末くらいまでは、間違いなく日本は温暖化対策に熱心に取り組み、世界をリードする一翼を担っていたが、今世紀に入ると徐々に遅れだした。そのきっかけは、01年にブッシュ政権が成立すると米国は「京都議定書」から直ちに離脱してしまったことである。これを見ていた日本の経団連の電気・鉄鋼・化学などの業界は、アメリカが参加しないのに、日本ばかりが損をするとの思いからか、気候変動対策に消極的になっていった。経産省が言い出したか、経済界の一部が言い出したかは定かではないが、この辺りから「京都議定書は、安政の不平等条約以来の不平等条約であり、こんな条約を結んだ日本は誤った選択をした」と言って憚らなかった。
当時、私は、ずいぶん大胆なことを言うとある意味感心していたが、何のことはない。アメリカが止めたからアメリカに従っただけである。当時も今も、日本の経済界と産業行政官の間には、アメリカのことしか見ていない人がいる。しかし、そのアメリカのオバマ政権は、8年間、終始気候変動に取り組み、フランスを中心とするEU諸国とともに中国・インドを巻き込み、「パリ協定」を作らせ、一年足らずの短期間で発効させた。
このパリの会議に、ビル・ゲイツを始め、たくさんの欧米企業のCEOが集まっていたのは、企業者として時代の流れの方向感覚の鋭さを示している。つまり、気候異変の現状から見るととんでもない異常気象とそれに伴う甚大な被害が予想されるなかで、これに対抗するための新しいビジネスを起こす確信を持っていたからであろう。
日本の企業者の中にも、もちろんそのようなセンスを持った人もいたと思うが、しかし、経団連・経産省に代表される一部産業界には、センスも力もなかったと言わざるを得ない。私は、この日本の遅れは、一世紀以上に亘って温室効果ガスを相当量出し続け、豊かな工業国を築き上げた日本としての責任感の薄さがまず以て気になるし、それとともに世界の産業界の潮流からさらに後れをとることも心配である。